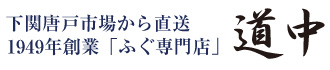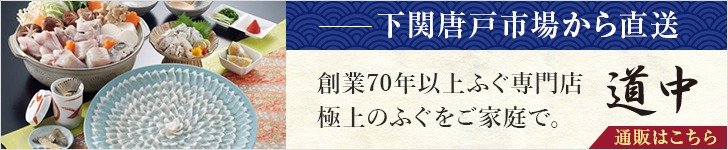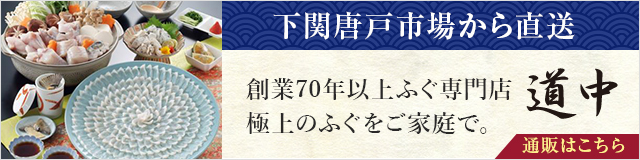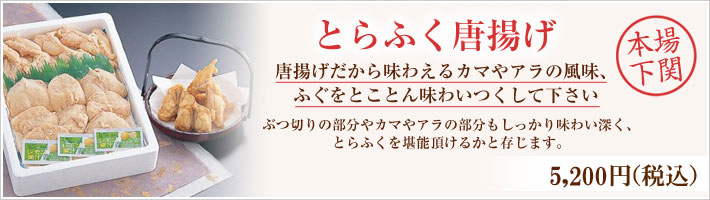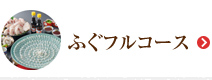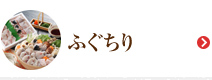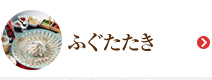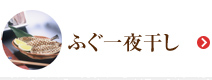毒があって少し怖いイメージを持たれがちなふぐ。
そんなふぐですが日本を代表する食材であり、ふぐに魅了された美食家も少なくはありません。
現在はふぐ調理師免許が定められており、厚生労働省なども可食部位などを明らかにしているため安心して食べる事ができるふぐですが、昔は多くの人がふぐは美味しいが危険な食べ物だと認識していました。
そのため食べるには食べて居ましたが、食べた後に不安になったりふぐ自体を食べる事を禁止したりしていたのです。
そんな危険なふぐですから多くのふぐは危険だよと言う短歌や俳句なども残されています。
ふぐが解禁をされたのは明治になってからの事だったのですが、どうやらふぐが解禁になったのには普通では考えられない奇跡があったようです。
ではどのような奇跡が起こってふぐの解禁がなされたのでしょうか。
当時のふぐ禁止令の背景
日本でのふぐ禁止令は豊臣秀吉によって出されました。
これは秀吉が1598年の朝鮮出兵の際に集結地とした山口県下関や北九州で出陣までの間にふぐを食べて死んでしまう兵士が続出しました。
主君を守る事が兵士の役目でありふぐの毒にあたって死んでしまうとは不名誉なことだとして腹を立て立て看板により「この魚食うべからず」とふぐを禁止にしてしまいました。
確かに現代の様に自由な世の中ではなく、武士は主君の為に命をかけろ!と教育をされている時代です。
そんな時代に主君の命を守れずにふぐで死ぬなんて本人にとっても不名誉ながら主君にとっても笑いものにされてしまう事でしょう。
更にいざと言う時に戦えない兵士はいりませんので、ふぐで死んでしまう兵士がいないようにするためにふぐを禁止したようです。
一説には町民も含めてフグの毒で死ぬのを防ぐためだったとされていますが、基本的に武士に対して厳しく罰していた点を見ると、町民の安全はまず考えていなかったでしょう。
本気で武士以外にもふぐを禁止していたなら現代のふぐ食は間違いなくなかったでしょうし、ふぐが庶民の食べ物として残ってきたはずもありませんよね。
更に秀吉が亡くなった後に各藩によって厳しく武士に対して禁止したのを考えても、やはり自分の保身のための禁止だったように思えますね。
ふぐ解禁の奇跡
明治になると今まで庶民の間では普通に食べられていたふぐが全国的に販売を禁止されてしまいます。
ですがそれでもこっそりと食べて居た人は多かったようです。
そんな中、内閣総理大臣の伊藤博文が日清戦争の講和条約を結ぶために1895年に下関を訪れました。
この時会議の場となったのが下関の春帆桜でした。
伊藤博文は過去にも春帆桜に訪れていたようですが、その時の対応がとてもよかったのかもしれませんね。
しかし1895年に伊藤博文が訪れた際にはちょうど時化の為にまったく魚が獲れない状態でした。
そこで苦肉の策で春帆桜の女将はふぐを出す事にするのです。
当時販売が完全に禁止されていたふぐですから、ばれたら投獄は免れないでしょうし毒によって体調が悪くなる人がいればそれ以上の罰が下っていたことでしょう。
しかし女将はそれを承知で提供したのです。
一目で見抜く伊藤博文
ふぐを提供したまではよかったのですが、どういうことか伊藤博文はすぐにふぐだと分かったようです。
というのも実は伊藤博文は長州藩の出身であり、若い時に食べた事があったのです。
長州藩と言えば桂小五郎や高杉晋作と言った異端児が多くいた藩です。
吉田松陰もふぐを食わざるの記という物を書いているほどで、長州藩ではふぐを食べる人が多かったようです。
伊藤博文は桂小五郎や高杉晋作と一緒に下関の豪商の男性を助けます。
この時お礼に食べさせてもらったのがふぐだったようで、伊藤博文にとってふぐは仲間との思い出の品だったようです。
しかし一応女将に聞きます「これは禁止されている魚ではないか?何かあって時には責任を取れるのか?」と。
女将も覚悟の上だとしか返せなかったでしょうが、その場でフグを清の人も日本の政府の人も食べたのですが誰一人として毒にあたる人がいませんでした。
伊藤博文は下関のふぐにどくは無し!と感激し、山口の県令(知事)に働きかけ1888年に下関はふぐ食禁止令から除外されました。
もしかすると仲間との思い出がよみがえり、毒が無かった事と思い出に伊藤博文は感動して働きかけたのかもしれません。
罰を免れるばかりかふぐ食が解禁されるとは・・・
おそらくふぐを提供した春帆桜の誰一人としてフグを出したことに対してお咎め無しであったことに対してホッとしたことでしょう。
しかしさらに下関ではフグを食べても販売しても良いようにしようと伊藤博文が働きかけてくれるなんて誰も思っていなかった事でしょう。
この時の女将の度胸と、伊藤博文の若き頃の仲間との思い出がきっと伊藤博文を突き動かしたのでしょう。
まさにふぐ食が認められたのは「棚から牡丹餅」と言うほかにないかもしれませんね。